
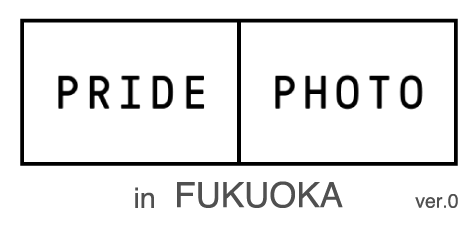
主催:SWANOIR合同会社
後援:オランダ王国大使館 | Embassy of the Kingdom of the Netherlands
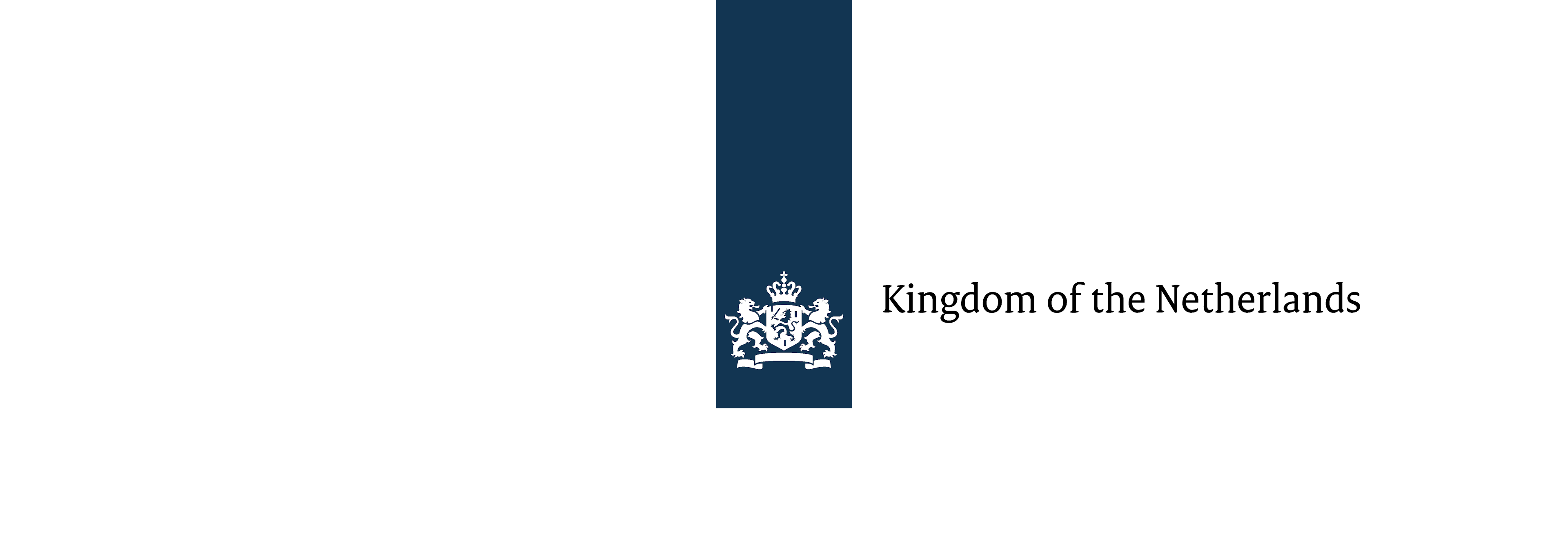
協力:平戸オランダ商館 / WITH THE STYLE FUKUOKA
2010年に設立されたアムステルダムを拠点とする「PRIDE PHOTO」は、写真とビジュアル・ストーリーテリングを媒介として、LGBTQIA+の多様な経験を称え、認知度を高めることを目的に、国際的な写真家、アーティスト等の作品を集めることで、LGBTQIA+コミュニティの多様性と多様性を表現することに努めている団体です。
今回は、世界各地から応募された「PRIDE PHOTO CONTEST 2023」にて受賞した作品を展示します。
date:
2024/5/8(水)~5/9(木)
13:00~20:00
入場無料・予約不要
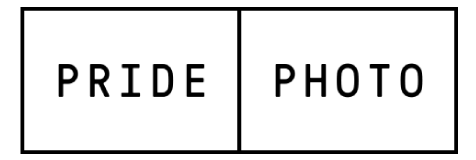
プライド・フォトについて
プライド・フォトは、2010年に設立されたアムステルダムを拠点とする非営利団体で、写真とビジュアル・ストーリーテリングを媒介として、LGBTQIA+の多様な経験を称え、認知度を高めることを目的としています。
国際的な写真家やアーティスト等の作品を一堂に集めることで、LGBTQIA+コミュニティの多様性と多様性を表現することに努めています。また、様々な表現を通して、ジェンダーとセクシュアリティの多様性を幅広く垣間見る機会を提供します。毎年開催される写真コンテストは、キャリアのあらゆる段階にある写真家が無料で応募し、参加できる開かれた機会です。
なお、プライド・フォトは、オランダの税務当局から公益団体(ANBI)として認定されており、同団体の活動は公益に寄与していると当局から認められている団体です。
プライド・フォト・コンテスト
2011年以来、プライド・フォトは、LGBTQIA+のストーリー、アイデンティティ、ビジュアル言語を紹介することを目的とした国際写真コンテストを毎年開催しています。コンテストはプロ・アマを問わず誰でも参加できるもので、「シングル」と「シリーズ」の2部門で構成されています。それぞれの部門では、第三者で構成される審査委員会と毎年選出されるゲスト・キュレーターによって総合受賞者が選出されます。
受賞者を決定する審査委員会は、毎年、写真界のプロフェッショナルから選出されるもので、この審査委員会が決定した受賞作品は、ゲスト・キュレーターによって、それぞれのテーマに焦点を当てた展覧会が企画されることになります。
本企画の背景
このページをご覧下さってありがとうございます。通常、弊社主催のイベントで企画の背景等を公開することはありませんが、今回の企画に関しては、背景や弊社の立ち位置をお伝えしておくべきと考え、以下に記載いたします。
Ahead of the event, I would like to share what motivated me to get involved with PridePhoto. While this is a complex topic to express, I believe it is important to share my perspective. Even if people from other countries may find it uncomfortable, please consider this as one way of thinking. Cultural perspectives and historical contexts vary by country, and this may create different understandings and assumptions between us, but I have shared my honest thoughts below.
オランダで感じる「多様性」のあり方
How ‘diversity’ is felt in the Netherlands
SWANOIRはオランダのEバイクメーカーの製品を使用した観光地向けEバイクシェア「Viker」をきっかけに、オランダや現地企業との関係を深めている企業です。
現在は、オランダに本拠を置く「RepairCafeFoundation」に加盟し、「リペア文化(捨てるのではなく直すことで環境負荷低減と地域コミュニティを増進する活動)」の一助も担っています。また、オランダ南部のアイントホーフェン市で行われる「Dutch Design Week」を定期的に訪問し、新しい企業の視察や連携を進めています。
オランダは「LGBTQIA+」に限らず、「安楽死」「大麻」など、賛否がありうるテーマについて、柔軟に取り組んでいる国です。
このようなテーマでは、ともすれば「賛成派が反対派を説得(その逆も)」しようとしている(ように見える)意見の衝突が、しばしば行われているように感じています。その点、オランダへの定期的な訪問を通して感じる特徴のひとつは「意見の一致を強要しない姿勢」です。
オランダでは(もちろん通年を通して生活し、様々な側面を見ればそうは言い切れないシーンは多いのかもしれませんが)、「他者に迷惑をかけない範囲においてそれぞれの考え方を尊重すること」、そして「自分の意見と他人の意見の一致を(暗黙的であれ)強要しないこと」のバランスが良いと感じています。これが「多様性」の基礎になるものであると感じており、自社の組織文化にも影響を受けています。
The Netherlands is a country that is flexible in its approach not only to ‘LGBTQIA+’, but also to other topics that can have pros and cons, such as ‘euthanasia’ and ‘cannabis’.
On such topics, I feel that there is often a clash of opinions in Japan, where the ‘pro’ side seems to be trying to persuade the ‘anti’ side (and vice versa). In this respect, one of the characteristics that I have sensed through my regular visits to the Netherlands is an ‘unforced consensus of opinion’.
In the Netherlands (of course, living in the Netherlands all year round and looking at various aspects, there may be many situations where this cannot be said), I feel that there is a good balance between ‘respecting each other's ideas to the extent that they do not cause problems for others’ and ‘not forcing (even implicitly) agreement between one's own opinion and that of others’. We feel that this is the basis for ‘diversity’, which also influences our company's culture.
SWANOIRにおける社会的課題に関する考え方
SWANOIR's approach to social issues
SWANOIRは主にIT領域やIoT領域で事業を行っている会社ですが、可能な限り社会的な課題に配慮した業務運営や開発を心がけています。
弊社が社会的課題に対して直接的に大きな効果を生み出すような解決策は実行できませんが、例えば、UIデザイン等のデジタル領域やIoT機器開発や各種イベントにおける物理的領域において、多様性に配慮した取り組みを推奨しています。
一例として、学校で使用するスマートフォンを前提としたアプリケーション開発受託において、諸般の事情でスマートフォンや携帯電話を利用できない生徒さんがサービスを利用できるように設計する等、製品やサービスのひとつひとつについて、利害関係者を広く深く捉えることを重視しています。
この考え方は、「社会システムによって、直接的・特定的な加害者はいないが不利益を被る人がいる場合、社会システムに乗って生活している人間には一定の責任がある」ということを前提としています。
SWANOIR is a company that operates mainly in the IT and IoT domains, but we try to operate and develop our business in consideration of social issues as much as possible.
We encourage diversity-friendly initiatives in the digital domain, for example in UI design, and in the physical domain, for example in the development of IoT devices and various events.
As an example, in application development based on smartphones used in schools, we focus on a broad and deep view of stakeholders for each of our products and services, such as designing services so that students who cannot use smartphones or mobile phones for various reasons can use them, etc.
This approach is based on the premise that when a social system causes people to be disadvantaged, although there is no direct or specific perpetrator, people living on the social system have a certain responsibility.
LGBTQIA+について
About LGBTQIA+
このような関心のもと、今回の企画のテーマである「LGBTQIA+」についても、最低限の配慮をしているつもりでした。
しかしながら、あるアーティストさん(実際のところはわかりませんが、その方のセクシャリティがマイノリティであることを間接的にお聞きしたことがありました)のエアチケットを準備する際に、「こういう場合は性別をどう聞くのが失礼にならないのか?」と社内で議論になりました。
これまでは、例えばアンケート設計の際に、性別を闇雲に聞かない、もし必要であれば「男性・女性」の2択にするのではなく第3の選択肢を提示する、程度のことは行っていましたが、「それさえしておけば良い」という思考停止に陥っていることを自覚した経験でした。
With this our thoughts, we thought we had given minimal consideration to the theme of LGBTQIA+.
However, when preparing an air ticket for an artist (we don't know what actually happened, but we had heard indirectly that the artist's sexuality was a minority), ‘How do we ask about gender in a case like this?’ was discussed internally.
In the past, when designing questionnaires, for example, we had done things like not asking gender in the dark and, if necessary, offering a third option instead of just two choices of ‘male/female’, but this experience made us realise that we had fallen into the trap of thinking that it was enough to just do that.
PRIDE PHOTO
PRIDE PHOTO
以上のような経緯がある中で、今回の企画についてオランダ商館からお声掛けいただき、今回展示している作品を拝見しました。
恥ずかしながら、国や文化が変わった場合、このテーマがこれほど重いものとなることや、ほんの数十年前まで起こっていたことについて、何も知りませんでした。このテーマを暗黙的に単なる個人の指向の話として捉えており、社会のテーマとして捉えていなかったことが原因だと考えます。
今回展示するPRIDE PHOTOの受賞作品は、このテーマについて時間的、空間的に想像を広げるきっかけとなり、このテーマの重要性を認識したことが今回の実施の契機です。
Given this background, when the Dutch Trading Post approached us about this project, I viewed the exhibited works.
I am embarrassed to admit that I had no knowledge of how weighty this theme becomes when crossing national and cultural boundaries, or about what was happening just a few decades ago. I believe this was because I had implicitly viewed it simply as a matter of individual orientation, rather than as a social issue.
The winning PRIDE PHOTO works being exhibited this time provided an opportunity to expand my imagination about this theme both temporally and spatially, and recognizing the importance of this theme became the impetus for implementing this project.
今回のイベント
Regarding This Event
今回は、将来的にこの企画を継続していくための、始まりとしての「0回目」という位置付けで実施しています。また、慎重に配慮しながら開催したく、限定的なPRにとどめています。
現時点で、「PRIDE PHOTO」における日本の受賞作品はまだなく、それどころか応募もない、と主催団体から聞いています。特に写真やアートに携わる方々は、ご関心をお持ちくだされば幸いです。
なお、本テーマのようなものを結果的にであれ経済的な利益につなげることはSWANOIRのポリシーに反するため、今後、入場料等のある企画を実施する場合も、透明性の高い収支管理に基づき寄付を行います。
We are conducting this as "Round 0" - positioning it as a beginning for potentially continuing this project in the future. Additionally, wanting to proceed with careful consideration, we are keeping the PR limited.
I've heard from the organizing body that currently there are few entries from Japan in "PRIDE PHOTO". We would be especially grateful if those involved in photography and art would take an interest.
Furthermore, as it goes against SWANOIR's policy to generate economic profit from themes like this, even incidentally, if we conduct events with admission fees in the future, we will make donations based on highly transparent financial management.
個人的な考えを多く含む内容で、お目汚しを失礼いたしました。最後までお読みくださりありがとうございます。
以上のような背景含め、ご賛同やご関心をお寄せ下さる方はぜひ会場にお越しください。
SWANOIR合同会社
CEO 百崎優


